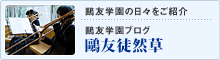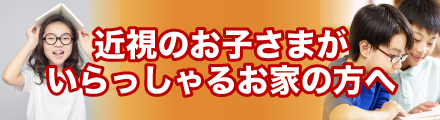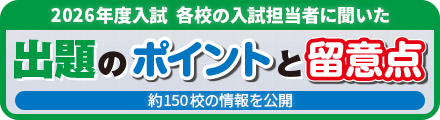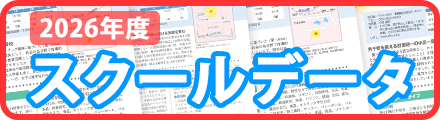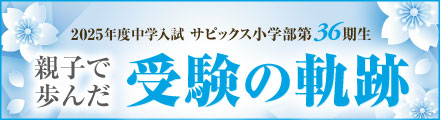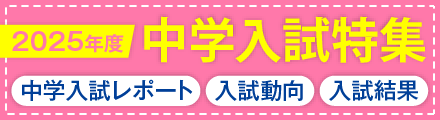- Top
- 学校行事/学校説明会
- 早稲田佐賀中学校:学校説明会レポート
学校説明会レポート
早稲田佐賀中学校
2025年5月24日(土)
早稲田大学系属校の強みと佐賀県の自然とを融合、未来を拓く学びの場
早稲田大学の7番目の附属・系属校として、2010年に開校したのが早稲田佐賀中学校・高等学校です。早稲田大学創設者の大隈重信の出生地は現在の佐賀市ですが、同校は同じ佐賀県内の唐津市につくられました。「進取の精神」「学問の独立」「地球市民の育成」を掲げ、「確かな学力と豊かな人間性を兼ね備えたグローバルリーダー」の育成をめざしています。
SAPIX代々木ホールで開催された説明会の冒頭、教頭の覚前宏道先生は、進学に関する重要な視点として、「進学先の基準は偏差値だけではない」「寮生活は子どもの人格・性格を更生する場ではない」「進学する大学で人生の幸不幸を決定するわけではない」という三つの考えを示しました。
同校は、かつての城(唐津城)の中にある全国でも珍しい立地の学校です。35都道府県や海外から生徒が集まっていますが、東京出身の生徒が最も多く、次いで福岡、佐賀、神奈川の順となっています。県外からたくさんの生徒が集まる理由の一つとして覚前先生は、同校が早稲田大学の系属校であることを挙げ、「内部推薦を利用し、早稲田大学へ進学できることが本校の特徴の一つです。2023年までの内部推薦は高校定員(240名)の50%に当たる120名でしたが、卒業生のがんばりが評価され、これから入学される皆さんは定員の約62%の148名まで枠が拡大されることになりました」と強調しました。
続いて、同校の教育の中核を成すものとして、覚前先生が挙げたのは「学習指導」「人材資源」「文武両道」「国際教育」「生徒主体」の五つです。
「学習指導」については、数学と英語の週テストを含む各種テストやベースアップ補習などで基礎学力をつけたうえで、日々の授業で思考力を伸ばします。また、中学3年間を通して行う探究活動では、中1は佐賀(唐津)、中2は九州、中3は日本というように視野を広げていき、実践力を鍛えます。一方で、学びの楽しさを体感する希望制の探究学習講座「ワセクエ」(早稲田佐賀クエスト)も年間で約100講座が開講されています。
「人材資源」については、早稲田大学のネットワークを生かして、元内閣総理大臣、元メジャーリーガー、宇宙飛行士など各界で活躍した卒業生による講演会を実施しているほか、各学部の教授による出前授業も行います。
部活動も盛んで、高いレベルでの「文武両道」を実践していることも紹介されました。高校についていうと、2年連続で全国優勝をしている弓道部、夏の甲子園にも出場した経験を持つ野球部などさまざまなクラブがあります。
英語教育とグローバル教育にも注力しており、4技能をバランス良く伸ばす方針の下、生徒はネイティブ教員による英会話授業やオンライン英会話レッスン、文化祭での英語スピーチコンテストなどを通じて学びを深めていきます。進級留学・個人留学・ターム語学研修などを利用する生徒も増えているとのことです。
「生徒主体」の取り組みとしては、生徒たちが主体的に企画・運営する行事も紹介されました。唐津市周辺を30㎞も歩き通す恒例の「100年ハイク」は、地元の人たちと触れ合う機会となっているそうです。
附設寮の「八太郎館」では、中高生全体の約7割に相当する750名以上が共同生活を送っています。寮生活において求められるものとして、「自己管理能力」「問題解決能力」「自主自立」を挙げた覚前先生は、「寮には教員も常駐し、お子さんの学習や生活をサポートしますが、自分の思いどおりになることばかりではありません。入寮するかどうかについては保護者の方が強制するのではなく、お子さん自身の希望や意思を尊重して決めてください」と語りました。
最後に、2026年度入試について説明がありました。2025年12月7日に新思考入試が行われます。一般入試は2026年1月12日と2月5日に、それぞれ九州と首都圏の各会場で実施されます。「1月入試の算数は1.2倍換算で判定される」ということも伝えられました。
 景勝地・虹の松原や唐津城など、美しい自然や史跡に囲まれたキャンパスが魅力。高校の部活動では、弓道部、野球部、サッカー部などが輝かしい成績を残しています
景勝地・虹の松原や唐津城など、美しい自然や史跡に囲まれたキャンパスが魅力。高校の部活動では、弓道部、野球部、サッカー部などが輝かしい成績を残しています
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎