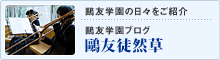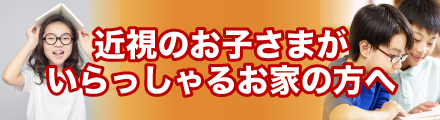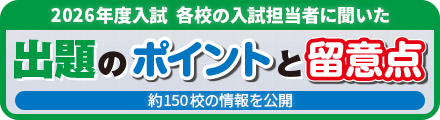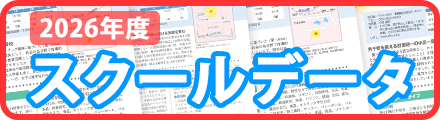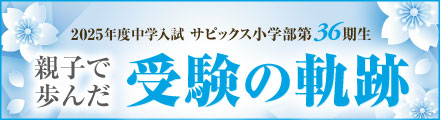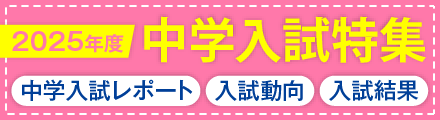- Top
- 学校行事/学校説明会
- 芝浦工業大学附属中学校:学校説明会レポート
学校説明会レポート
芝浦工業大学附属中学校
2025年5月30日(金)
中高大が連携した独創的な教育を実践し、グローバルな理工系スペシャリストを育成
芝浦工業大学附属中学高等学校は、同じ豊洲にある芝浦工業大学との連携教育とSTEAM教育を特徴とする共学の中高一貫校です。2021年にカリキュラムを一新して探究活動を充実させ、ものづくりと最先端技術に触れる独自の理工系教育を推進しており、2025年春の現役進学率は95.9%でした。芝浦工業大学へは55.2%で、これを含め全体の85.1%が理工系の学部・学科に進学しています。
この日の説明会では、最初に校長の柴田邦夫先生があいさつに立ち、同校が求める生徒像と、育成したい能力について説明しました。「本校では中高大の連携教育の下、世界で活躍する理工系人材の育成をめざしています。理工系に振り切った唯一無二の学びを実践し、生徒が理科に対する興味を持ち、主体的に学ぶ意欲を持てるように教育環境を整えています。こうした本校の方針に共感してくださる方の入学をお待ちしています」と呼び掛けました。
続いて、教頭の斎藤貢市先生が、同校が力を入れている探究教育について説明しました。その特徴は、理工系の知識で社会課題を解決に導く「SHIBAURA探究」です。中1・2ではIT(Information Technology)とGC(Global Communication)の二つの「探究」に、中3ではその集大成となる「総合探究」に取り組みます。まず、ITでは、テクノロジーで社会課題を解決できるようになることを目標に、中1から多くのITツールを体験してアイデアを形にしていく手法を習得します。GCでは、多様性への理解を深めることを目標に、グローバルな視点を持ち、グループで協働しながら問題解決型の学習に臨みます。中1では東京の文化を学び、中2では3泊4日の長野農村合宿を通して地域振興や多様性について考えます。そして、中3では2週間の海外教育旅行(アメリカ3コース、オーストラリア1コースから選択)と探究を組み合わせたプログラムに参加して国際性を身につけます。一方、「総合探究」では生徒の興味・関心に基づいてチームを編成します。互いの強みを生かし、弱みを補い合いながら未来を創造するためのアイデアを考案し、プロトタイプの実装と検証を進めます。高校ではこうした経験やスキルを基に、個々にテーマを見いだして探究を進め、より研究色の濃い学びへと発展させていきます。
続いて、探究以外の教育内容について、広報部長の杉山賢児先生が説明しました。同校では、「理工・連携・言語・探究」の四つを教育の柱としています。そのうち理工系教育についてはSTEAM教育の一環として、全教科で科学技術との関連を学ぶ「ショートテックアワー」や、大学教員などを招いて教科書にない大掛かりな実験・実技に取り組む「サイエンス・テクノロジー・アワー」(中3)などを実施していることが特徴です。連携教育としては、パスタを使って強度の高い橋を作る「工学わくわく講座」(中1)、芝浦工業大学が開発した教育用ロボット「ビートル」を1人1台製作する「ロボット講座」(中2)、デザイン工学の楽しさを体感できる「ものづくり体験講座」(中3)があります。そして、言語教育とは、日本語・英語・コンピュータ言語の三つの言語を学ぶということです。論理的にことばを操る技術を訓練するとともに、プログラミングの基礎などに挑戦します。日本語については「見る・考える・伝える」を念頭に自分のことばで正しく伝える技術を磨く「ランゲージアワー」(中1・2)や、プロが指導する「話し方講座」(中3・高1)を開講します。英語についても使う機会は豊富です。
最後にサピックス出身の中1生2名が登壇し、学校生活や将来の夢について、「クラブの先輩の面倒見がいい」「オリエンテーション合宿で友人がたくさんできた」「学校での学びを生かして一級建築士になり、人のためになる施設を造りたい」などと語ってくれました。
なお、2026年度の中学入試では、第1回と第2回の受験科目に論理社会(リスニング問題なし)が加わり、従来の国語・算数・理科と合わせた4科に変更されるとのことです。
 新聞記事検索など、さまざまなデータベースが導入されている図書室は知的好奇心を刺激する空間で、探究学習の拠点として活用されています
新聞記事検索など、さまざまなデータベースが導入されている図書室は知的好奇心を刺激する空間で、探究学習の拠点として活用されています
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎