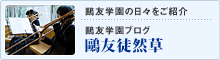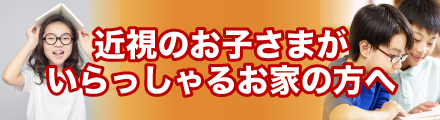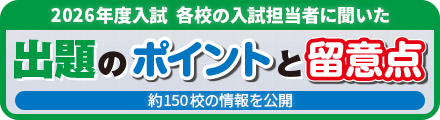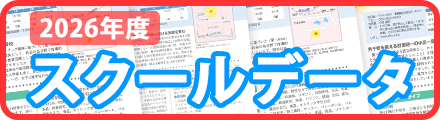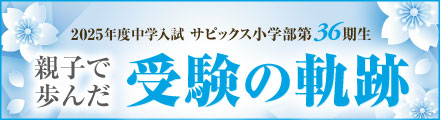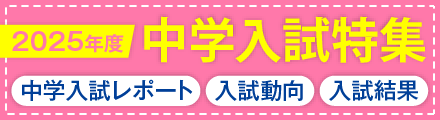- Top
- 学校行事/学校説明会
- 開智日本橋学園中学校:学校説明会レポート
学校説明会レポート
開智日本橋学園中学校
2025年9月3日(水)
国際バカロレアの理念を取り入れた、主体性を育む「探究型の学び」を実践
開智日本橋学園中学校・高等学校は「平和で豊かな国際社会の実現に貢献するリーダーの育成」を教育理念に掲げ、国際バカロレア機構(IB)の中等教育プログラム(MYP)および後期中等教育プログラム(DP)の認定校として、探究型の学びを実践しています。
この日、あいさつに立った副校長の藤井由紀子先生は、「本校では『自ら考え、判断し、主体的に行動する』を合言葉にしています。IBの学びでは『知識の習得だけでなく、問いを深め、考える力を育てること』や『対話と探究を通じて主体的に学ぶ姿勢』などを大切にしていますが、これらは開智学園の学びにも通じるものがあります」と語りました。また、IBの特徴として「10の学習者像」や「Approaches to Learning(ATL)スキル」(学び方を学ぶスキル)が明確に示されていることを紹介し、教員の指導によって、思考力・自己管理力・コミュニケーション力など、主体的な学びに必要な力が育まれていると説明しました。
次に、広報部長・教頭の井田貴之先生が学校の特徴について紹介しました。最初に挙げたのは、「自分らしく成長できる文化がある」という点です。井田先生はその具体例として、テーマを決めて他者と対話を重ねる「哲学対話」の授業に触れ、「この授業では『話は最後まで聞く』『人の意見は否定しない』というルールを設けています。これにより、生徒は安心して、みんなの前で意見を主張でき、多様なことに臆せず挑戦するようになるのです」と話しました。
学校行事や部活動はもちろん、学校説明会や校舎案内ツアーも生徒主体で企画・開催しており、教員はそのサポートに徹しています。校舎案内ツアーのスタッフには、毎年多くの新入生が立候補しますが、“採用面接”や“実践型の研修”は上級生が行うなど、適任者を決める段階から生徒たちに任せているそうです。
生徒の主体性を伸ばすために、全教科で探究学習を導入しているのも特色です。疑問・仮説・検証・発表のサイクルを軸に、失敗から得られる学びも重視しています。「たとえば、生物の授業で行う『豚の心臓の実験』では、心臓のどの構造を観察したいかを班ごとに決めます。そのため、切り方や観察方法も目的に応じて変わります。教科書どおりに進めるとは限らず、失敗と改善を重ねますが、だからこそ理解も深まるのです」と井田先生は話します。また、宿泊行事もすべて探究型のフィールドワークとして実施されています。
教育の特徴として、「社会とつながるグローバルな環境」が整っていることも紹介されました。「英語を使う」ことを重視しており、美術・技術・社会などを段階的に英語で学ぶ仕組みがあります。留学制度も充実しています。また、国内・国外、いずれの進路を希望する者にも柔軟にサポートしていて、多くの生徒が将来の目的を明確にしたうえで進学先を選択しています。これについては、性的少数者(LGBTQ)の環境改善を考えていた生徒が「自分のやりたいことは日本よりオランダのほうが進んでいるから」と卒業後、海外の大学に進学した例を挙げました。
コース編成に関する説明もありました。IBの中等教育プログラムに相当する最初の4年間は、計6クラスの生徒が3コースに分かれて学びます。母体である開智学園の探究型学習を軸に、IBの国際的要素を取り入れた「リーディングコース(LC)」が4クラス、「LC」の内容に加えて一部の教科を英語で学ぶ「デュアルランゲージコース(DLC)」が1クラス、帰国生など英語力の高い生徒を対象とした「グローバル・リーディングコース(GLC)」が1クラスとなっています。「LC」では、中1・2の2年間は日本語で探究型の学びを実践し、中3からは美術・技術を英語で学びます。海外大学への進学も視野に入れた「DLC」では、日本語と英語の両方で探究型の学びを行い、「GLC」では英語・社会・総合学習・美術・技術・家庭科などをネイティブ教員が英語で指導しています。
 JR・都営浅草線「浅草橋」駅、JR「馬喰町」駅、都営新宿線「馬喰横山」駅の3駅が徒歩10分圏内にある好立地。高3は受験勉強に集中しやすいよう隣接する別館で学びます
JR・都営浅草線「浅草橋」駅、JR「馬喰町」駅、都営新宿線「馬喰横山」駅の3駅が徒歩10分圏内にある好立地。高3は受験勉強に集中しやすいよう隣接する別館で学びます
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎