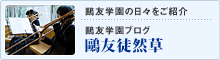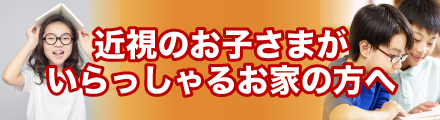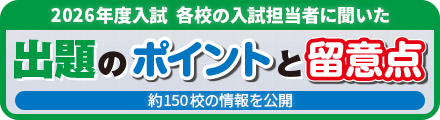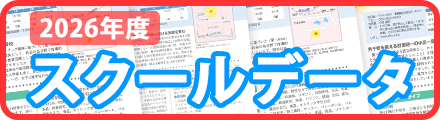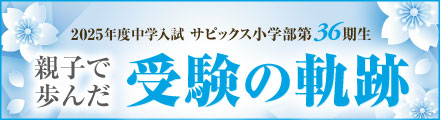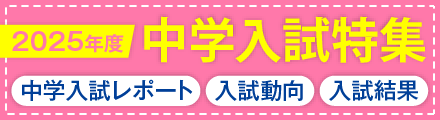- Top
- 学校行事/学校説明会
- 東京電機大学中学校:学校説明会レポート
学校説明会レポート
東京電機大学中学校
2025年9月3日(水)
理科・情報・探究を柱に、体験を重視した教育プログラムで個性と適性を引き出す
東京電機大学の前身である夜間の「電機学校」は、1907年に2人の青年技術者、廣田精一と扇本真吉がエンジニアを育てるために22人の若者を集めて創立されました。現在は工学部・未来科学部・システムデザイン工学部など、5学部を設置する理工系総合大学へと発展しています。その系列校である東京電機大学中学校・高等学校では、東京電機大学の初代学長で、ファクシミリの生みの親として知られる丹羽保次郎が掲げた「技術は人なり」という理念に基づき、「人間らしく生きる」を校訓に掲げ、「豊かな心・創造力と知性・健やかな身体」を兼ね備えた人材の育成をめざしています。
この日の説明会では、最初に校長の平川吉治先生がその校訓に触れ、「生徒たちには、なぜ勉強するのか、何のために生きるのかを意識させなければならないと思っています。本校での学びを通して、6年間、考えたり学んだりしながら、社会で生きていくための指針となる倫理観や価値観を見つけてほしいのです」と語りました。
続いて、中学教頭の磧谷和樹先生が学校の概要と教育内容について説明しました。中学は1学年5クラス(1クラス約30名)、高校は1学年7クラス(1クラス約40名)で構成され、男女比は2対1です。中1・2では学力や男女比に応じて均等にクラス分けを行い、中3・高1では習熟度別クラスを設けて効率的な授業を展開します。高2・3では文系と理系に分かれ、理系・文系の比率は6対4です。なお、中高一貫生と高校からの入学者は別クラスで学びますが、高3の自由選択科目では同じ教室で学ぶ機会もあります。
続いて磧谷先生は、同校の教育の特色である「理科教育」「情報教育」「探究学習」「グローバル教育」について説明しました。まず、「理科教育」については、「実物に触れたときの感動」を大切にして、中高6年間で100種類以上に及ぶ実験や観察を行うことを紹介しました。実験用具を自作する機会も多く、中学の物理分野では実験用具や試料を保管する「実験BOX」を生徒一人ひとりが持ちます。磧谷先生は「自分で実験用具を作れば、ものづくりの思考や、ものをていねいに扱う気持ちが育ちます。自分の実験用具なので、自宅に持ち帰って修理・改良することも可能です」と話します。「情報教育」は40年以上も前から続く伝統的なプログラムです。授業では、1人が1台を所持するタブレット型のPCや、コンピュータ室に設置された約50台のパソコンを活用して、情報専任教員が2名体制でチームティーチングを行います。「探究学習」は週1時間設けられており、正解のない問いに挑む思考力を養います。中3では、その集大成として、各自が決めたテーマに沿って研究した成果を卒業論文にまとめ、ポスター発表を行います。「グローバル教育」としては、福島県のブリティッシュヒルズでの英語研修(中3~高2)、マレーシア英語研修(中3~高2)、カナダ短期留学(高1)などの希望者対象のプログラムがあります。
なお、「学び残しゼロ」をめざす同校では、今年度から「放課後学習支援」を導入しました。具体的には、「学習メンター」を務める難関大学の学生が7~9名常駐し、ロールモデルとして生徒に寄り添いながら、学習や進路の相談に応じるというものです。
最後に磧谷先生は、「本校では、部活動や体験学習、学校行事など『好きを極める時間』も大切にしています。生徒には好きなことに没頭する活動を通じて、集中力・忍耐力・想像力を養ってもらいたいのです。そして、たくさんの失敗を経験し、そこから学び、“困難を乗り越える力”を体得してほしいと願っています」と語り、説明会を締めくくりました。
 JR中央線「東小金井」駅から徒歩5分。充実した運動施設に加え、約6万5000冊の蔵書を誇る図書館も備えています
JR中央線「東小金井」駅から徒歩5分。充実した運動施設に加え、約6万5000冊の蔵書を誇る図書館も備えています
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎