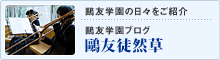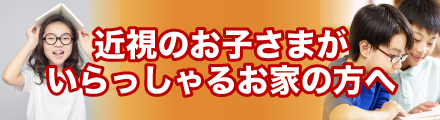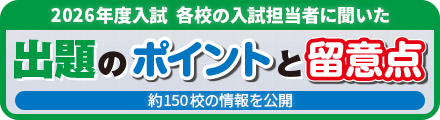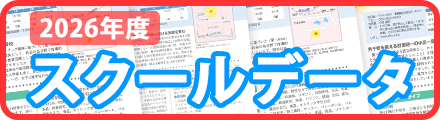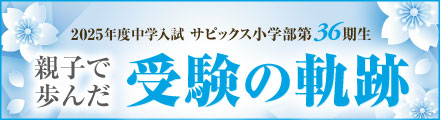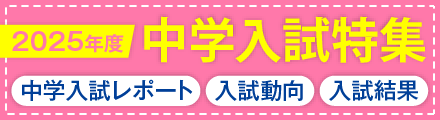さぴあインタビュー/全国版
学ぶ意欲をかきたてる
多彩な教育プログラムで
挑戦するマインドを育む
本郷中学校・高等学校 校長 木村 友彦 先生

自学自習を促す「本数検」
下級生に受け継ぐ「朝読書リレー」

校長 木村 友彦 先生
神田 主体的に学習できる人になってほしいというお話がありましたが、貴校には自学自習の意欲をかきたてる教育プログラムが充実しています。なかでも特徴的なのは、オリジナルの検定制度「本数検」ではないでしょうか。
木村 本数検は「本郷数学基礎学力検定試験」の略称です。数学科の教員が問題を作成し、生徒はそれぞれの得点に応じて「級・段」が認定されます。「夏休み明けに何級を取ろう、何段を取ろう」と個々が目標を設定して、そこに向けて長期休暇中にどう勉強すればよいかを考え、準備します。
神田 本数検を始めてから「数学オリンピック」や「ジュニア数学オリンピック」にチャレンジする生徒が増えたそうですね。数学オリンピックで取得したメダルや賞によっては大学の推薦入試で有利になります。自分ががんばってきたことが数年後の大学受験に生かせるとなれば、チャレンジのしがいもありますね。
木村 そうですね。ただ、結果として入試に活用することはあっても、それが目的ではなく、チャレンジ精神といいますか、対外的なコンテストで自分がどれぐらいがんばれるのか挑戦してみたいという思いで生徒たちは参加しているようです。
クラブ活動もそうです。たとえば、科学部が「日本物理学会Jr.セッション」で入賞したり、地学部が「とうきょう総文(全国高等学校総合文化祭東京大会)」に出場したり、歴史研究部が「全国高校生歴史フォーラム」で入賞したりしています。そうしたものにチャレンジするのは、自分の力が対外的にどう評価されるのかを知りたいからであり、わたしたちも「どんどんチャレンジしよう」と伝えています。本数検も始めて20年ほどたちますが、テストで良い点を取るためというより、自分が決めた目標を達成するために、長期休暇の間にどう力を蓄えるべきかを考えるという発想が長い年月をかけて根づいてきている気がします。

上/式典や学校集会などでも利用される永井体育館は、バスケットコート2面が取れる広さ
下/図書室の蔵書数は約4万5000冊。十分な閲覧スペースがあり、図書委員会の活動も活発です
安酸 「朝読書」も長く続けていらっしゃいますが、読んだ本を紹介する機会もあるそうですね。そのような形で互いに啓発し合うような読書体験は、学力を高めたり、知見を広げたりすることに有効にはたらくと思います。
木村 朝読書を導入した当初は、一日が始まる始業前の10分間、心を落ち着けて本を読もうという試みでした。そこから発展して、自分が読んでおもしろかったと思う本を紹介する「朝読書リレー」が始まり、今では朝の良い習慣になっています。以前は冊子にまとめていましたが、今は一人ひとりが端末を持っているので、各自がみんなに読んでほしいと思う本をアップするという形で行っています。
これも、最初は、打ち込んだものをフォーマットに流し込むことがなかなかうまくできませんでした。すると、高3の図書委員で、コンピューターに詳しい生徒が、読みやすいフォーマットに流し込むシステムを作ってくれました。そのおかげで、朝読書リレーが格段に充実したものになりました。受験勉強で忙しいなか、高3生が後輩たちのために自分の技能を生かして動いてくれたことはうれしいですね。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎