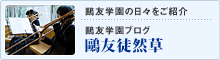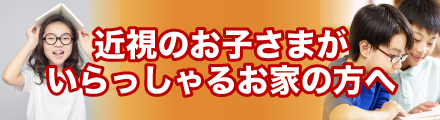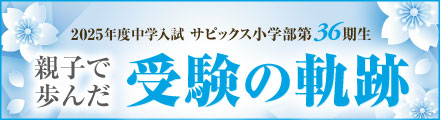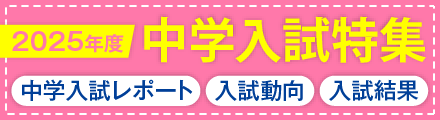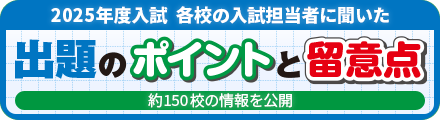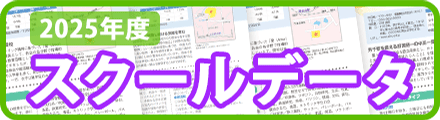さぴあインタビュー/全国版
チャレンジする意欲を伸ばす
開かれた教育環境が
未来を創る力を育てる
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 校長 高際 伊都子 先生

インプットとアウトプットを重ね
確かな言語表現力を養成する

上/バスケットボールのコートが2面ある第2体育館。授業やクラブ活動のほか、全校集会でも利用されます
下/図書室は吹き抜けの設計で、明るく心地良い空間。上階は閲覧室になっています
堀口 教科の話に移りますが、カリキュラムにはどのような特徴がありますか。
高際 特徴はいくつかあります。まず国語と英語の授業数が多いことです。低学年ほど多く、表現活動には時間を割いています。授業では、インプットとアウトプットのバランスを大事にしています。「読む」と「書く」、「聞く」と「話す」という、この対になる4技能に、英語でも国語でも多くの時間を割り当てて、言語力をしっかり高めていきます。
この4技能は相互補完の関係にあります。よく聞けない子はよく話せないし、読めない子は書けません。だから英語の授業でも、インプットをしたら、それをアウトプットができるように構成しています。特に中1の英語ではこれを積み重ねます。そして、一定の力がつくまでは中間テストなどは行わず、1回ごとのチャレンジで細かく評価をします。学期末にはそのチャレンジの総和が出てきますから、「試験前にちょっとだけ勉強すればいい」というやり方は通用しません。
中3以降は教科ごとの連携を密にしています。たとえば、英語の授業で理科的な内容を扱うなら、理科の先生にも英語の教材になっていることを意識してもらい、理科でも英語でもきちんと理論的なことを伝えるようにしています。問題を解ければいいだけの知識の扱い方はしません。教科の垣根を低くして、たとえば社会の特別授業の内容が英語にも役立つことが普通にあるのだと、生徒たちにわかってもらえるようにしています。数学を学ぶのは問題を解くためではないことが、メッセージとして伝わるような授業ですね。そのなかで「数学はおもしろい。もっと突き詰めたい」と思ったら、大学で専攻すればいいのであって、高校の段階で専攻を縛ることはしたくありません。
神田 「SOLA」の説明文にも、「さまざまな分野の学びを同時に扱うから『リベラルアーツ』と名付けた」と書かれていました。ふだんの授業でもそれを実践されているのですね。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎