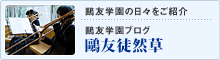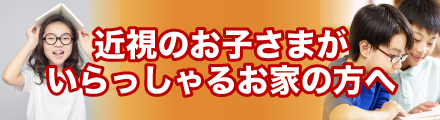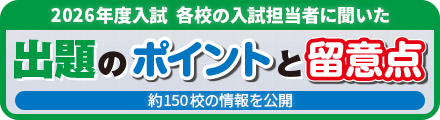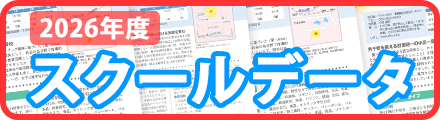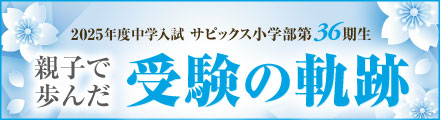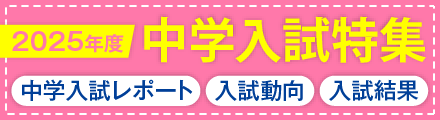子育てインタビュー
将棋の普及活動に取り組む女流棋士がアドバイス
自分の頭で考え、試行錯誤しながら、
みんなで楽しもう「 将棋の世界」

北尾 まどかさんKitao Madoka
(きたお まどか)●1980年生まれ。東京都出身。6歳ごろに将棋を覚え、高校1年でそのおもしろさに目覚める。女流育成会を経て、2000年10月にプロデビュー。2010年に株式会社ねこまどを設立し、女流棋士・経営者として対局と将棋普及活動の両方に携わる。2013年8月、女流二段。2023年7月に引退。現在は、将棋イベントや将棋教室の運営、オリジナル将棋グッズの制作・販売など、将棋を広めるために国内外を飛び回る日々を送っている。著書に『やさしくてよくわかる! はじめての将棋レッスン』(日本文芸社)など。
将棋は日本の伝統文化であるとともに、人と人とをつなぐ知的なコミュニケーションツールでもあります。今回は、女流棋士として活躍され、現在は将棋教室の運営や「どうぶつしょうぎ」の考案など、多様な活動を通して将棋の普及に尽力されている北尾まどかさんにインタビュー。将棋のおもしろさや楽しみ方、さらには将棋上達のポイントなどについて語っていただきました。
将棋人口倍増をめざして
さまざまな活動を展開
広野 北尾さんが考案された「どうぶつしょうぎ」は、盤面のマス数や駒の種類を少なくし、駒にはかわいい動物が描かれています。また、駒を進める方向もきちんと示されていて、初心者が将棋の世界を体験するのにうってつけですね。
北尾 将棋は、世代を超えて楽しめる日本伝統のボードゲームです。古代インドで生まれたゲームがルーツとされ、チェスなどのように似たゲームは世界中にありますが、「取った駒を自分の味方として使える」点がユニークですね。ただ、覚えるべきことが多く、ゲームとして楽しめるようになるまでに時間がかかるのが難点です。実際、わたし自身も子どものころに将棋を始めたときは、駒の漢字や、動かし方を覚えるのに苦労しました。ある時、動かす方向が書かれているチェスの駒と出合い、「こういう工夫が将棋の世界にもあればいいのに」と思ったものです。そうした子ども時代の体験が、どうぶつしょうぎを考案する原点となっています。
広野 ちょっとした工夫でスタートのハードルを下げ、気軽に楽しめるようにして、まずは「好き」になってもらおうというわけですね。
北尾 子どもにとって、「できる」という体験は大きな喜びになります。音楽の世界、たとえばピアノなどでは、楽譜を読めるようになるまでのメソッドや、初心者が演奏を楽しむノウハウが確立されています。そのことが愛好家の拡大に一役かっているわけです。
一方、将棋は、かつてはそういう工夫が十分ではありませんでした。将棋も初心者向けに工夫をすれば、もっとたくさんの人たちに楽しんでもらえるのではないか。そう考えて、さまざまな取り組みをしてきました。女流棋士として対局を重ねる一方で、初心者を対象とした将棋教室やイベントも開催してきました。まだ字も読めない小さな子と触れ合っていくうちに、たとえ短い時間のなかでも勝負の楽しさや、自分で駒を選んで動かす喜びを経験してほしいという思いが膨らみ、どうぶつしょうぎが生まれたのです。お子さんはもちろん、これまで「難しそう」と敬遠していた大人にも手に取っていただけたことが、うれしかったですね。そうした普及活動を拡大してくために、「ねこまど」という会社を設立しました。
広野 北尾さんの将棋教室には、女の子の参加も多いそうですね。
北尾 将棋は男性のものという思い込みがあるようですが、本来は性別に関係なく楽しめるゲームです。これまで、あまりにも男性比率が高くてしり込みしていた女性の方々にも将棋を楽しんでもらい、将棋人口を倍増させたいというのが、わたしの願いです。母数が増えていけば、いずれはトップに勝ち上がる女性の棋士も出てくるでしょう。囲碁の世界などは、すでにそうなりつつありますよね。
広野 算数や数学についても、最近は性差に関する固定観念がなくなってきています。サピックスでも算数でトップの成績を取る女子が増えてきました。将棋の世界でも女性棋士の活躍が期待されますね。
父のことばに後押しされ
高校生のときに将棋の道を志す

サピックス教育事業本部
本部長
広野 雅明
広野 北尾さんご自身は、なぜ将棋に興味を持ち、棋士をめざされるようになったのですか。
北尾 実は、わたしが将棋を本格的に始めた時期は、ほかの棋士と比べて遅いほうなのです。子どものときに、いろいろなゲームの中の一つとして父から将棋のルールを教わったのですが、当時は駒を使った「山崩し」や「回り将棋」を楽しみながら、時々、本将棋の真似事をする程度でした。オセロやトランプはできましたが、本将棋は幼いわたしには難しすぎたのです(笑)。
その後、高校生になってようやく将棋のおもしろさに目覚めました。高校生にもなると、自分でやりたいことを自分で見つけだし、それを実行できます。周りの生徒が大学受験の勉強に励んでいる時期に、将棋にどっぷりとはまり、将棋のことを本で調べたり、相手を見つけて対局したりすることに夢中になりました。自分でやりたいことを好きなだけ追求していった結果、すぐに強くなったので、「こんなに好きなのだから、一生かかわっていきたい」と、将棋の道に進むことにしたのです。
広野 ご家族からは、どのような反応がありましたか。
北尾 母は大学に進学してほしいと考えていたようですが、父は「自分の好きな道に進むほうがいい」と後押ししてくれました。「音楽や将棋など、さまざまな機会を与えたなかで将棋というものを選んだ。ならばそのことを応援したい」と考えたようです。わたし自身が「学校の勉強をもう少しがんばったほうがいいのでは」と迷ったときも、「将棋と決めたのなら、将棋に専念し続けなさい」と発破をかけてくれました。
広野 将棋の世界では、師匠に弟子入りしていろいろなことを学ぶそうですね。
北尾 将棋の世界でプロをめざす場合、師匠の下について将棋そのもののほか、将棋界のしきたりや棋士としてのふるまい方などについて教えてもらいます。わたしの場合は、将棋会館で教えてくださる指導棋士の先生に、西村一義九段(当時)を紹介していただきました。月1回のペースでほかの門下生と共にさまざまなことを学び、本当にお世話になりました。
わたしの時代は、ひたすら対局をして将棋漬けの生活をし、プロの養成機関で開催される半年間のリーグ戦で優勝すると、晴れてプロに、女流2級になるというしくみでした。そこからは公式戦を重ねながら勝ち星を積み上げ、昇級していくのです。そうした日々のなか、20代半ばぐらいから将棋の普及活動に徐々に目を向けていきました。
『やさしくてよくわかる!
はじめての将棋レッスン』
北尾 まどか 著
日本文芸社 刊
1,045円(税込)
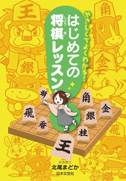
「将棋をはじめよう」から始まって、駒の動かし方、王のつかまえ方など、将棋のルールを順を追って説明。かわいいイラストを通して子どもが理解しやすく、「また将棋がしたい!」「もっと学びたい!」と思わせる要素が盛りだくさんです。保護者へのアドバイスも各章にあり、親子でいっしょに楽しめる内容となっています。
『新装版 どうぶつしょうぎ』
北尾 まどか ルール考案
小学館 刊
2,200円(税込)

3×4マスの盤と、8枚の駒で遊ぶミニ将棋。かわいい動物の駒には、駒を動かせる方向に印がついていて、小さな子どもでもルールを楽しく学ぶことができます。将棋の楽しさに触れながら、集中力や思考力を養う知育玩具です。対象年齢は4歳以上。9×9マスの本将棋版(4,950円・税込)もあります。
- 25年7月号 子育てインタビュー:
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎