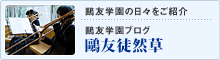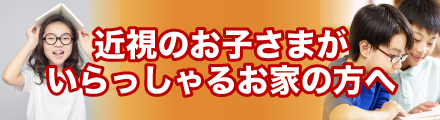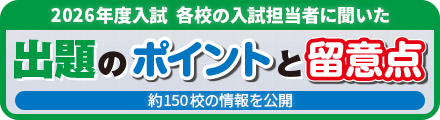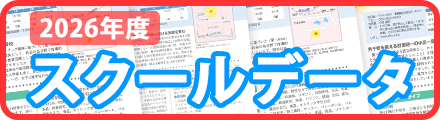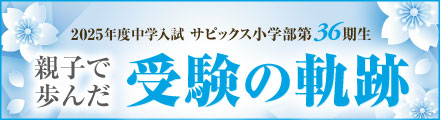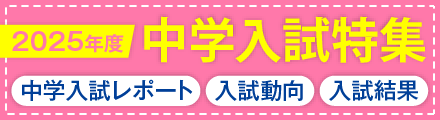子育てインタビュー
将棋の普及活動に取り組む女流棋士がアドバイス

自分の頭で考え、試行錯誤しながら、
みんなで楽しもう「 将棋の世界」
将棋は日本の伝統文化であるとともに、人と人とをつなぐ知的なコミュニケーションツールでもあります。今回は、女流棋士として活躍され、現在は将棋教室の運営や「どうぶつしょうぎ」の考案など、多様な活動を通して将棋の普及に尽力されている北尾まどかさんにインタビュー。将棋のおもしろさや楽しみ方、さらには将棋上達のポイントなどについて語っていただきました。
勉強の王道は詰将棋、棋譜並べ
最近はあえてAIを活用しない棋士も
広野 将棋では対局以外に、日々の研鑽も大切だと聞きます。どのような勉強をなさっているのですか。
北尾 今も昔も変わらない将棋の勉強の王道は、詰将棋を解くことと、先人が対局で指した手の記録を読み、それをそのとおりに盤面に再現する棋譜並べです。
詰将棋は、王将をどうやって詰むかを考える、思考力を鍛えるパズルのようなものです。初心者用の一手詰めや三手詰めから、何十手、何百手とかかる大作もあります。江戸時代の詰将棋の名作を集めた『詰むや詰まざるや』という本もあって、「プロをめざすならこれを解きなさい」と言われるほど、棋士には有名です。難しい問題だと、それこそ1週間かけて考えても全然詰まなかったりするのですが、わからなくても考えること自体がプラスになります。わたしも詰将棋がすごく好きで、いくらでも考え続けられます。
棋譜並べは、自分のめざす戦型や自分の棋風に近い棋士、あこがれの棋士の棋譜を並べて勉強するというものです。最近のタイトル戦で指された棋譜を並べて、今の時代に流行している指し手を分析したり、逆に江戸時代の棋譜なども残っているので、それを並べて昔の考え方を研究したりします。どのような棋譜を見て、何を取り込んでいくかは、棋士によって違います。
広野 AIを使った研究についてはいかがですか。
北尾 もちろん、わたしも取り入れています。今やAIは棋士にとって必需品といってよく、大半の棋士がAIを相手に対局したり、過去の棋譜を調べたりして研究を重ねています。ただ、最近の若手の棋士の間では、あえてAIに頼らず、自分の力で考え、地力を養おうという考え方が、また出てきているようです。おもしろいですね。
広野 AIを道具として使いこなすにしても、結局、自分の実力がないとうまくいかないですからね。
指導のポイントは
「なるべく教えない」こと

広野 サピックスでは、昨年、日本将棋連盟や東急電鉄と連携して、受験勉強に入る前の小学3年生を対象に、3か月間将棋の授業を行う「将棋教室ラボ」というプログラムを実施し、北尾さんには講師として将棋の指導に協力していただきました。
実際の授業をわたしも見学していたのですが、子どもたちの集中力の高さに驚かされました。将棋がうまくなる子どもは、どこが違うのでしょうか。
北尾 まずいえるのは、将棋の才能がある子が将棋で伸びるとは限らないということです。将棋が得意だけど、「あまり勉強したくない」「勝負事が性に合わない」「ほかにやりたいことができた」といった理由でやめてしまうケースが少なからずあります。才能の差よりも大切なのは、将棋が好きかどうかです。「毎日でも将棋教室に行きたい」「誰でもいいから相手を見つけて対局したい」「どうしたら勝てるのか」などと言ってくる子は、圧倒的に強くなります。そういう意味では、「好きになること」自体が上達に最も必要な才能かもしれません。
広野 スポーツでも芸術でも勉強でも同じことがいえます。上達するためには、みずから鍛錬を重ねる意欲が不可欠となりますが、そのベースとなるのが「好き」という気持ちですからね。
北尾 今お話しされた「みずから」という点も大切で、自分で考えられる子は、やはり伸びます。将棋を始めたお子さんにありがちなのが、近くにいる大人の顔色を見ながら「これでいいのかな」と指すタイプです。それでは自力で指すことが難しくなってしまいます。どの駒をどこに指すか、自分で決められるようにならなくてはなりませんから、わたしたちが教えるときは後ろから見守って、なるべく「こう指したほうがいい」といった指導はしないように心がけています。必要な要素はヒントとして与えますが、あとは「どう選んでもいいんだよ」と認めるのです。指し手のパターン、定跡を知ることも重要ですが、それに頼りすぎると、スタート時は速く上達しても、いずれ伸びなくなります。パターンに頼りすぎず、まずは自分自身で試行錯誤し、自分で納得しながら指し方を覚えていくことが大切です。
自分の頭で考えて勝てたという経験を積んでいくと、一手一手をしっかりと決断し、記憶できるようになるので、上達していきます。いずれは対局後に相手と共に対局内容をつぶさに振り返る「感想戦」を行うことも可能になります。それができるようになれば、さらに上達の道が開けます。「なるべく教えない」「ゴールそのものを示さない」ということを、周りの大人は心がけてほしいと思います。
広野 そうですね。子どもが「好きなこと」を見いだし、それに夢中になって取り組み、力を伸ばしていけるような環境を整え、あとはなるべく口を出さず、見守ることが大切ですね。本日はありがとうございました。

| 子どもの個性に合わせた指導を ねこまど こども将棋教室 |
|
| 東京都新宿区の四谷校を本校として開講されている、子ども向けの将棋教室です。通常の将棋教室では対応が手薄になりがちな10級以下の子どもたちの指導を重視。子どもの個性に合わせた多様なプログラムを用意しながら、級ごとに明確な目標を設定して、20級から段位まで体系的な指導を行っています。 | |
| 詳しくはこちらから | |
| ▶ nekomado.com/kids/ |
|
- 25年7月号 子育てインタビュー:
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎