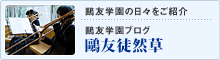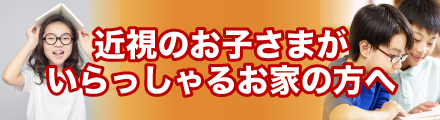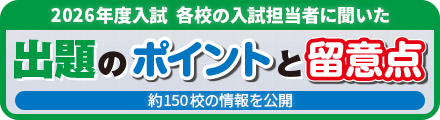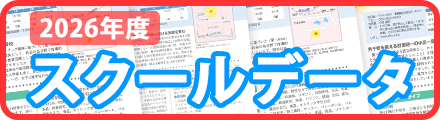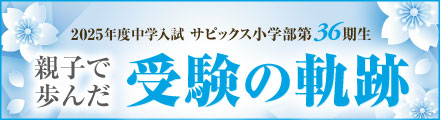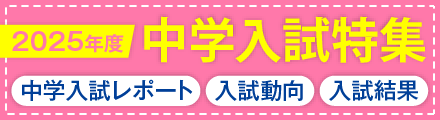この人に聞く
次世代に伝える新しい金融教育
お金は「増やす」のではなく
社会に「生かす」ことに意味がある

2022年度から高校において金融教育が必修化されました。お金はわたしたちの生活に必要不可欠ですが、その役割や活用法を正しく理解するのは大人でも難しいものです。お金とは何なのか、お金を通じて幸せになるとはどういうことなのか。元・外資系証券会社のトレーダーで、『お金のむこうに人がいる』『きみのお金は誰のため』の著者でもある田内学さんにお話を伺いました。

お金の向こう研究所 代表
社会的金融教育家・作家
田内 学 さん
金融トレーダーから作家に転身
人生を変えた有名編集者との出会い
 SAPIX YOZEMI GROUP
SAPIX YOZEMI GROUP
共同代表
髙宮 敏郎
髙宮 田内さんは、2021年に『お金のむこうに人がいる』で作家としてデビューし、2作目の『きみのお金は誰のため』は約27万部を記録するベストセラーとなりました。まずは、本を執筆するに至った経緯を伺えますか。
田内 わたしは大学を卒業して17年間、外資系証券会社のトレーダーとして働いてきました。日々、経済や金融の動きを注視していくなかで、メディアで取り上げられている経済問題と、自分が感じている問題意識に、大きな隔たりを感じるようになってきました。しかし、トレーダーという立場では、その違和感を世の中に発信する術がありません。そんな折に、高校の後輩でもある有名編集者と会う機会があり、今の社会に対して自分が感じていること、そして、その問題意識が世の中にうまく伝わっていないジレンマについて話しました。
髙宮 漫画『ドラゴン桜』や『宇宙兄弟』などを手掛けた佐渡島庸平さんですね。
田内 そうです。すると彼は、その話を言語化して、本にしてみたらどうかと提案してくれました。「その主張が正しければ、安倍首相(当時)にだって伝わりますよ。それが本を出すということなのです」と。そのことばに打たれ、会社を辞めて、本の執筆に専念することを決意したのです。
とはいえ、これまでとはまったくベクトルの違う仕事ですから、しばらくは佐渡島さんのもとで、漫画家との打ち合わせに同行したり、自分からもアイデアを出したりして勉強させてもらうことにしました。ただ、彼は非常に多忙なので、イチからノウハウを教えてもらう時間はありません。そこで考えたのが、彼のドライバー役を買って出ること。そうすれば、打ち合わせの行き帰りの1時間はじっくり話ができると思ったのです。そこでは、「抽象的な概念をいかに具体的に表現するかが大事」など、自分の考えを言語化するために必要なアドバイスをたくさんもらいました。そうした助言をもとに、約2年をかけて書き上げたのが『お金のむこうに人がいる』です。
髙宮 世間の反応はいかがでしたか。
田内 反響は非常に大きく、佐渡島さんのことばどおり、安倍元首相を含む自民党議員が参加する勉強会で、この本の内容を説明する機会にも恵まれました。確かに、本を書いたことで政治家の方に自分の主張を伝えることはできましたが、だからといってすぐに政治が変わるわけではありません。いくら政治家が「日本を変えよう」と本気で思っていても、それを実現する道のりには、さまざまなしがらみが存在するからです。そこで、日本のこれからを長期的かつ真剣に考えてくれるような若者やその保護者、教育に携わる方々が読んでくれるような本を書くことで、世の中を変えていきたいと思うようになりました。その思いを込めたのが2作目の『きみのお金は誰のため』です。
「他者」や「社会」の視点を持ち
力を補う仲間を見つけることが大事
髙宮 『きみのお金は誰のため』を通して伝えたいことについて、教えていただけますか。
田内 現代社会では、年収や資産の多寡がその人のステータスのようにみなされていますが、あらためて「お金は何のためにあるのか」を考えてほしいと思ったのです。たとえば、ロールプレイングゲームの世界では、主人公が旅をしながら武器や仲間を増やし、最終的にボスとの戦いに勝つことがゴールとなります。では、わたしたちの人生のゴールは何でしょうか。人は生きていくにあたって、平等に与えられている“時間”を使って、能力や経験を高めていき、それによって他者からの信用を得ます。そうして自身の人的資本から社会的資本を作り出す過程で、自然と金融資産が増えていき、総合的に幸福を得ることが人生のゴールといえるのではないでしょうか。しかし、現代社会は、偏差値や年収など、数値化できるものだけが過度にフォーカスされ、「他者」や「社会」という視点が抜け落ちています。それゆえに、幸福を感じにくい世の中になっているように思えるのです。
髙宮 お金はあくまで手段に過ぎないのに、それを得ることが目的化されているということですね。
田内 そうです。経済はよく「カネ・モノ・ヒト」に分けて語られますが、議題になりやすいのは「カネ」です。これは、今まで「モノ」や「ヒト」が充足していたからであり、圧倒的に「ヒト」が足りなくなるこれからの時代は、ここに大きなパラダイムシフトが起きるだろうと見ています。
14世紀のヨーロッパでも、ペストの流行によって人口が2~3割減少し、急激な労働力不足に陥りました。その結果、何が起きたかというと、領主と農民の立場の逆転です。これまで農奴として縛りつけられてきた労働者が引く手あまたとなり、より条件の良いところへと移動し始めました。そうした状況では、「カネ」より「ヒト」の価値が相対的に高まり、従来の価値観が通用しなくなるわけです。
髙宮 すでに日本でも労働者不足の問題は深刻化しています。「ヒト」が足りない時代に、必要なこととは何でしょうか。
田内 大切なのは「本当に役立つことを見つける力」です。社会に役立つことを見つけて、そこに自分のスキルを生かす。もし、それが自分だけで成し遂げられない場合には、苦手なことは素直に認めて、協力者を探せばいいと思います。自分の利益だけを求めるなら、協力者を見つけるのは大変です。しかし、社会に役立つことを見つけているのなら、実はそんなに難しくはありません。
ロールプレイングゲームの世界もそうですよね。「悪を倒す」という目的を持っているから、自分の苦手なことを補う魔法使いや戦士が仲間になって一緒に戦ってくれるわけです。実は、社会のためを考えて生きていくほうがうまくいきやすいのです。
家族や学校も社会を形成する一部
身の回りからできることを見つけよう

髙宮 中高生を対象に講演される機会も多いそうですが、これまでの印象的なエピソードがあれば教えてください。
田内 ある中高一貫校に出掛けたときのことです。講演を終えたわたしのところに、男女8人くらいのグループが近づいてきて、次のような質問をしました。「日本はこんなに大変な状況なのに、どうして大人は危機感がないのですか」「危機感を持ってもらうために、どんな行動をとればいいですか」と。大人よりもシビアに現実を直視し、何をすべきか真剣に考えている若者の姿に衝撃を受けると同時に、「日本の未来は明るい」と感じました。そういう子どもたちに、どうやってバトンを手渡し、どうやったら選択肢を増やせるのか。それが今の大人に求められている使命なのだと痛感させられました。
昨今、学校で金融教育を学ぶことの意義が取り沙汰されていますが、金融教育が果たすべき役割は、お金をいかに「増やすか」ではなく、いかに「活用するか」を教えることだと思います。何か社会にアクションを起こそうと思ったときには、まとまったお金が必要になるかもしれません。そのとき、どういう仕組みを使えばお金を集められるのか、本質的かつ実践的な手段を伝えることこそ重要なのではないでしょうか。
髙宮 田内さんは、これからの時代を担う若い世代にどんなことを期待していますか。
田内 自分たちも社会をつくっている一員だと認識して、少しずつでいいので、できることや変えるべきところを見つけていってほしいと思います。社会というのは、自分の手の届かない、遠いところの話ではありません。ふだんの生活に密接している家族や学校もまた、社会を形成する一部です。初めは小さな一歩でも、それが連動していけば大きな変化につながるということを忘れないでほしいですね。
- 25年5月号 この人に聞く
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎