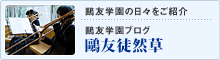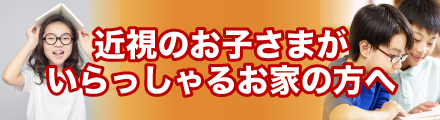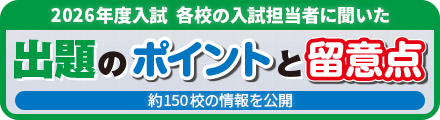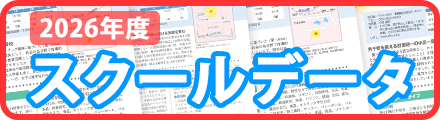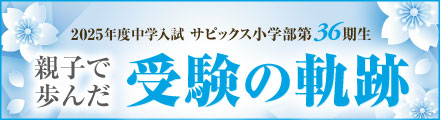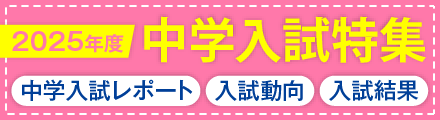共立女子中学高等学校は、1886年に創立された共立女子職業学校から発展した伝統女子校です。同校で1963年から続けられているのが、高3生が体育祭で披露する「荒城の月」のダンスです。伝統のプログラムを演じた大変さや、踊りに込めた思いについて、高3生のダンス係の生徒と、体育科教員の荻江瞳先生に伺いました。
伝統を支えてきたダンス係
未経験者にも優しく指導
 左から、高3生でダンス係を務めたY.S.さん、
左から、高3生でダンス係を務めたY.S.さん、
体育科教員の荻江瞳先生
共立女子中学高等学校の体育祭で、高3生が披露する「荒城の月」のダンスは、60年以上にわたり受け継がれてきた、同校の象徴といえるものです。このダンスが始まったきっかけについて、体育科教員の荻江瞳先生は次のように説明します。
「お茶の水女子大学の教授で、『学校ダンスの第一人者』と呼ばれた故戸倉ハル氏が、当時さまざまな唱歌に振りを付ける取り組みをされており、その一つが『荒城の月』のダンスでした。体幹を鍛えるうえでもぴったりの振り付けで、共立女子用にアレンジして踊り始めたのがきっかけだと聞いています」
高3生が300人そろって踊る「荒城の月」は、初披露以来、共立女子の体育祭に欠かせない演目となり、先輩から後輩へと受け継がれています。その伝統を支えてきたのが、ダンス係の生徒たちです。1クラスにつき4人選出され、教員から指導された振り付けをほかの生徒たちに教え、全員が同じ動きで踊れるようにするという重要な役割を担っています。
2025年度7月の体育祭でダンス係を担当した高3生のY.S.さんは、ダンス未経験者への指導が特に大変だったと振り返ります。
「共立女子では、中1から体育でダンスを踊る機会がとても多いのですが、『荒城の月』ほどレベルが高いものではありません」と荻江先生は話します。Y.S.さんも同意しながら、「動きも複雑なので、ことばだけでは伝わりません。自分で動きを実際に見せたり、振り付けの動画を作っていつでも見られるようにしたりと、動きを理解しやすいように工夫しました」と説明します。
練習は高2の11月から始まり、「直前期には朝練や昼練もほぼ毎日実施していた」とY.S.さん。「勉強の合間に行うので、みんなとても大変だったと思います。ただ、苦手な生徒ほど積極的に参加して、ダンスでわからない点があればどんどん質問をしてくれたので助かりました」と振り返ります。
また、上手に踊ることよりも楽しく踊ることを大切にして、クラスメートにポジティブなことばを掛けるように心がけました。「その思いが伝わったのか、本番後、ある生徒に『最初は踊るのが苦手だったけれど、みんなで一緒に練習しているうちに楽しくなった』と言ってもらいました。本当にうれしかったことを覚えています」
全体練習はわずか2回
本番では心を一つにして踊り切った
300人がそろっての全体練習は、予行練習と本番当日の朝の2回のみ。300人が一堂に会する機会は限られているため、予行練習で先生から受けたアドバイスをもとに、各自が自宅で最後の練習を行います。
「『荒城の月』の振り付けのなかで、300人が八つのグループに分かれて円をつくり、それを維持しながら移動して踊る箇所があるのですが、この円を崩さないようにするのが特に難しいところでした。予行練習でもなかなかそろわなかったので、本番できちんとできるか不安でした」(Y.S.さん)
そうして迎えた体育祭本番。「荒城の月」を踊る前には代表の生徒が口上を述べますが、Y.S.さんはこの大役を任されました。「入場時は何も考えられないくらい緊張していましたが、マイクの前に立ったとき、『わたしが作品を背負っているんだ』と緊張を振り払い、会場にいる先生方や保護者の方に、思いが伝わるように感謝の気持ちを述べました」
Y.S.さんが立派に生徒代表の役目を果たした後、いよいよ演舞が始まります。参加者の全員が、「300人で踊る機会は、もう一生に一度しかない」と考えていたに違いありません。思いを一つにして、全身で「荒城の月」の世界観を表現します。Y.S.さんが心配していた円をつくる振り付けも、本番ではぴったりとそろいました。
「共立生は本番に強く、ここぞというときに力を発揮してくれると信じていました。今年も高3生が最大限のパフォーマンスを発揮することができて、とてもうれしかったです。わたしは高3クラスの担任でもあり、当日は全体を見なくてはならず、クラスの様子を落ち着いて見られませんでしたが、それでもダンス係を信頼していたので心配はありませんでした。期待に十分応えてくれました」と荻江先生。来場した保護者や教員のなかには、感動で涙を流す方もいたそうです。
荻江先生はこの「荒城の月」の踊りを通して、生徒たちに「やり抜く力」を身につけてほしいと言います。「一人ではやり遂げられないことでも、みんなとがんばれば達成できるという経験をしてほしいと毎年考えています。上手に踊ることが重要なのではありません。がんばってきた過程こそが大切だと思います」とのことばに、Y.S.さんもうなずきながら、「踊りを通して、仲間と協力する楽しさを感じることができました。この伝統ある踊りを、後輩たちにも継いでほしいと思います」と話しました。
最後に、Y.S.さんと荻江先生は受験生にメッセージを送りました。
「多くの出会いがある学校で、特に先生と生徒の距離が近い点が魅力です。体育祭では先生が参加する競技もあって、とても盛り上がります。たくさんの出会いをしたいという方には、ぴったりの学校だと思います」(Y.S.さん)
「いろいろなタイプの生徒がいますが、誰もが楽しいと思える学校だと感じています。出会いにあふれた、自分の可能性を見つけられる学校なので、ぜひ一度、見学に来ていただければと思います」(荻江先生)
 総勢300人による壮大なパフォーマンス。心を一つにして美しい舞を踊ります
総勢300人による壮大なパフォーマンス。心を一つにして美しい舞を踊ります
 「荒城の月」を踊る前に、生徒を代表して口上を述べるY.S.さん。保護者や教員に感謝の思いを伝えました
「荒城の月」を踊る前に、生徒を代表して口上を述べるY.S.さん。保護者や教員に感謝の思いを伝えました

![]()


 左から、高3生でダンス係を務めたY.S.さん、
左から、高3生でダンス係を務めたY.S.さん、 総勢300人による壮大なパフォーマンス。心を一つにして美しい舞を踊ります
総勢300人による壮大なパフォーマンス。心を一つにして美しい舞を踊ります 「荒城の月」を踊る前に、生徒を代表して口上を述べるY.S.さん。保護者や教員に感謝の思いを伝えました
「荒城の月」を踊る前に、生徒を代表して口上を述べるY.S.さん。保護者や教員に感謝の思いを伝えました