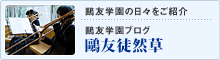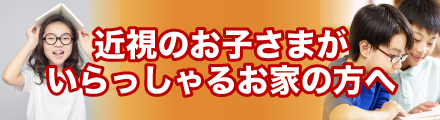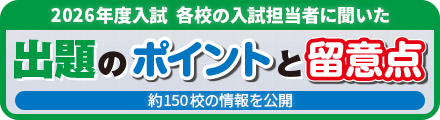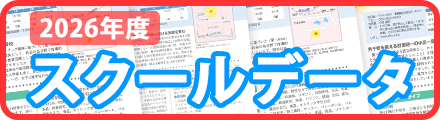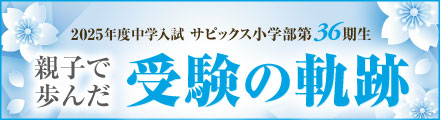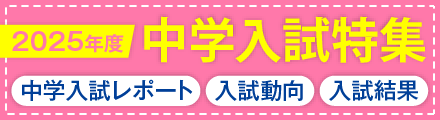AI技術の急速な進化を受け
会議のテーマも変化していく
 倫理科 小野浩司先生
倫理科 小野浩司先生
同校の高校生有志による活動「AI倫理会議」は、人工知能と人間社会のかかわりを倫理的な視点から考える取り組みで、毎年「倫理憲章」を策定することを目標に掲げています。「きっかけは、倫理の授業でデカルトの『我思う、ゆえに我あり』という考え方について扱ったことでした」と話すのは、倫理科の小野浩司先生です。「人間の尊厳は理性に基づくのか、もしAIが理性を持ったなら人間と同等とみなせるのか。そんな問いについて生徒たちと話し合うなかで、人工知能を題材にした会議を開こうと考え、2016年に活動を開始しました」と説明します。翌2017年に第1回AI倫理会議を開催。以降は年1回のペースで継続され、毎年10名前後の高校2年生を中心とする有志が主体となって運営しています。会議には他校の生徒も加わり、活発な議論が展開されています。
この活動は、生徒がすべてを主体的に進めています。専門家の講師の選定と講演の交渉から、資料・報告書の作成、会議の運営までを自分たちで担います。毎年2学期に動き出し、年内に講師を決定。その後、新聞記事や最新のAI関連ニュースなどを調べて事前資料をまとめ、月に1度ほどのペースで集まり準備を重ねます。資料の発送やアンケートの実施などもすべて生徒が行います。こうした過程を通して、計画の立て方や情報整理、連絡調整といった実社会で必要とされるスキルを自然に学んでいきます。
「近年はAI技術の急速な発展を受け、会議のテーマも変化してきました」と先生は話します。2022年の第5回以降は、フェイク動画や生成AIの倫理的課題が大きなテーマとなり、時代の最先端に即した議論が行われています。講師には研究者や大学教授、企業のガバナンス担当者など、各界の第一線で活躍する専門家が招かれます。ときにはデジタル大臣を迎えることもあり、生徒たちにとっては、現代社会の問題点などを知る貴重な機会となっています。「こうした専門家の話は大きな刺激となり、自分の無知さや、さらに広い世界が存在することを気づかせてくれます。進路を考えるきっかけとなることも多く、生徒の将来に確かな影響を与えています」と先生は述べます。
どう活用し、どう向き合うか、
立ち止まって考える
 AI倫理会議の報告書を内閣府に提出。施行されたばかりのAI法の話なども聞くことができました
AI倫理会議の報告書を内閣府に提出。施行されたばかりのAI法の話なども聞くことができました
会議で得た成果は報告書としてまとめ、内閣府にも提出します。その時の生徒たちの様子について、先生はこう話します。「内閣府の担当者との意見交換のなかで『本当の知識とは何か』と問われ、生徒は答えに詰まりました。テレビや新聞で得た情報を“本当”と信じてよいのか。インターネットの情報はなぜ“本当”でないとされるのか。そうした根本的な問いに向き合う体験は、情報社会を生きるうえで欠かせない学びとなっています」
AI倫理会議は、AIの動向や関連事項を知るだけではなく、自分で調べ、考え、仲間と議論し、専門家の話を聞きながら、AIとどのように共生していくかを主体的に考える場なのです。「AIを『怖い存在』ととらえるのではなく、どう活用し、どう向き合うかを立ち止まって考えることこそが、この活動の意義といえます。将来、企業でAIを導入する立場になったときに役立つ知見も得られるでしょう」と先生は語ります。
この活動は部活動のように顧問や先輩が指導するものではありません。過去の資料を参考にしながらも、基本的にはゼロから自分たちで築き上げていきます。時には失敗することもありますが、試行錯誤を含めてすべてが学びとなります。学校も「まず行動してみること」を大切にし、挑戦を後押ししています。
今後は発足10周年に向けて、さらに活動を広げる計画があります。コロナ禍以降はオンライン会議が中心でしたが、企業訪問や大学研究室の見学など、現場を直接訪れて学ぶ機会を増やしていく予定とのことです。
最後に、先生は次のようなメッセージを送りました。「清泉女学院中学高等学校は、生徒のエネルギーを尊重し、一人ひとりが挑戦できる環境を整えています。AI倫理会議はその象徴的な活動であり、生徒が主体的に考え、行動し、失敗からも学びながら未来を切り開く力を育む場です。ここで得た経験は、生徒たちが社会に出たとき、確かな自信となり、実践力につながっていくはずです」
 有志の生徒が自主的に集まり、議論を重ねます
有志の生徒が自主的に集まり、議論を重ねます
 自分たちで考え、行動し、チャレンジする機会が豊富にあります
自分たちで考え、行動し、チャレンジする機会が豊富にあります

 清泉女学院中学高等学校は、カトリックの聖心侍女修道会を設立母体とする学校です。豊かな自然に囲まれた広大なキャンパスで、これからの社会で必要となる新しい学びを実践しています。人工知能との共生を、倫理的視点から調べ、考え、行動する「AI倫理会議」の活動について、倫理科の小野浩司先生に伺いました。
清泉女学院中学高等学校は、カトリックの聖心侍女修道会を設立母体とする学校です。豊かな自然に囲まれた広大なキャンパスで、これからの社会で必要となる新しい学びを実践しています。人工知能との共生を、倫理的視点から調べ、考え、行動する「AI倫理会議」の活動について、倫理科の小野浩司先生に伺いました。
![]()


 倫理科 小野浩司先生
倫理科 小野浩司先生 AI倫理会議の報告書を内閣府に提出。施行されたばかりのAI法の話なども聞くことができました
AI倫理会議の報告書を内閣府に提出。施行されたばかりのAI法の話なども聞くことができました 有志の生徒が自主的に集まり、議論を重ねます
有志の生徒が自主的に集まり、議論を重ねます 自分たちで考え、行動し、チャレンジする機会が豊富にあります
自分たちで考え、行動し、チャレンジする機会が豊富にあります