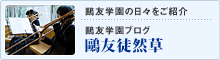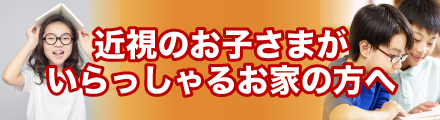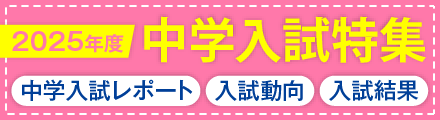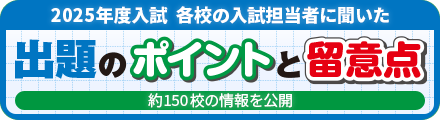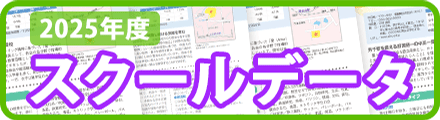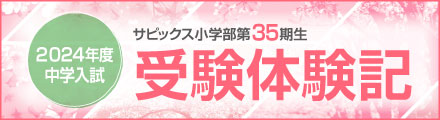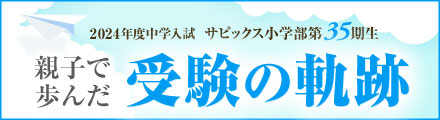さぴあインタビュー/関西情報
主体的に学び、
卒業研究に取り組みながら
みずから考える力を身につける
神戸大学附属中等教育学校 校長 齋木 俊城 先生

卒論で研究力の基礎を身につける
探究学習「Kobe プロジェクト」

校長 齋木 俊城 先生
立見 貴校は創設当初から、総合的な学習の時間を利用して、探究学習を行っていますね。
齋木 はい。この探究学習は「Kobeポート・インテリジェンス・プロジェクト(Kobeプロジェクト)」という名称です。低学年ではグループで研究活動を行います。3年生以上になると、同じような分野で卒業論文を書きたいと思っている生徒たちが各学年から数名ずつ集まり、15~16人で一つのゼミが構成されます。この学年を超えた共同ゼミが、時間割上では、Kobeプロジェクトの時間になるのです。
進め方は大学のゼミに近く、各自が研究していることを発表し、ほかのメンバーはそれに対して意見を出します。そのため、自分の研究は放課後や帰宅後に行います。生徒の負担は相当ありますが、このゼミには、先輩と後輩とが刺激し合って成長できるという効果もあります。現在、本校に47人いる教員のうち33~35人が何らかのゼミを担当していますが、ゼミの運営方法は指導教員の裁量に任せています。神戸大学の先生が直接指導してくださるものもありますし、大学院生たちもサポートしてくれます。これも高大連携の一つといえるでしょう。
石原 そうしたKobeプロジェクトを導入された背景を教えてください。
齋木 本校が創設された15年前は、「探究」ということばがまだ一般的ではなく、本校でも「卒業研究」「卒業論文」といった呼び方でスタートしました。その背景には、「大学で学ぶ力をしっかり身につけてきてほしい」という大学側の強い要望がありました。大学が中学・高校と大きく違うのは、大学では研究を行うという側面が強いことです。ですから、まず研究する力の基礎となるリサーチ・リテラシーを身につけることが求められます。そのために、本校では卒業論文を書くのです。また、卒業論文をまとめることによって、「積極的な大学選び」をしてほしいという大学側の要望もあります。単に合格できそうな大学を受験するというのではなく、「あの大学でこういう事柄を学びたい」という目的意識を持って大学を選び、進学してほしいということです。このように、本校の生徒に卒業論文を書かせてほしいという大学の要望の狙いは、「研究に必要なリサーチ・リテラシーを身につけてほしい」「目的意識を持って大学に進学してほしい」という2点に集約されます。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎