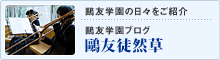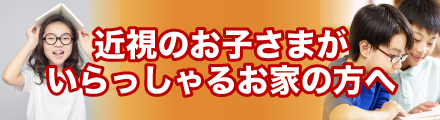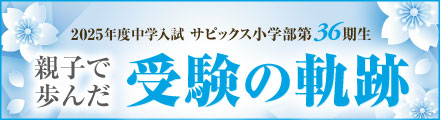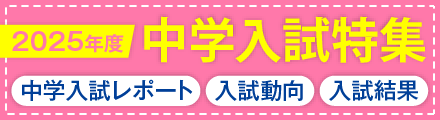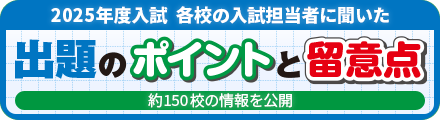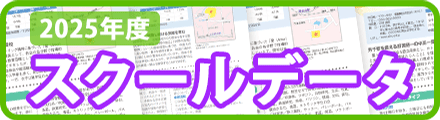さぴあインタビュー/全国版
多様な経験を盛り込んだ
バランスの取れた教育を通して
確かな学力と豊かな人間性を形成
早稲田中学校・高等学校 校長 笹倉 和幸 先生

設立当初から貫く「誠の精神」
「誠」とは「うそをつかないこと」

SAPIX YOZEMI GROUP
共同代表
髙宮 敏郎
髙宮 創立125周年記念事業として、2020年から建設が進められていた新校舎がすべて完成しましたね。新しい校舎はどんな印象ですか。
笹倉 「バンカラ」な早稲田のイメージとはまったく違う、モダンな設計となっています。全体的にスペースをゆったりと使い、壁の多くをガラス張りにしたので、明るく開放的な空間となりました。今回新しくなったのは、正門から入って右手の3号館と、その先の興風館です。3号館には理科実験室や情報教室などが入り、興風館には体育館をはじめとする運動施設、ラーニングカフェ、図書館などがあります。3号館と興風館の間が吹き抜けのプラザになっていて、さらにほかの校舎ともつながっているので、中学生と高校生の交流がしやすくなりました。
髙宮 来年には創立130周年を迎えられますが、あらためて学園の沿革をご紹介いただけますか。
笹倉 本校は1895(明治28)年、大隈重信の教育理念に基づき、坪内逍遙、市島謙吉、金子馬治が中心となって創設されました。1948(昭和23)年に高校が設置され、さらに教育の充実と発展を見据えて1979年に早稲田大学の系属校となりました。そして1993(平成5)年に高校募集を停止し、6年一貫校となりました。
髙宮 笹倉先生は早稲田大学政治経済学部の教授をされながら、2023年に校長に就任されました。学校に対して、どのような印象をお持ちですか。
笹倉 「生徒が優秀」のひと言に尽きます。本校は文系・理系の区別なく、基本的にすべての教科を学びますが、本当にまんべんなく指導されていて、学習意欲も高いと感じました。
髙宮 笹倉先生は、生徒目線でとてもわかりやすいお話をしてくださると、御校の先生方から伺いました。
笹倉 早稲田大学の建学の精神は「学問の独立」です。そのために必要なのは、独立した精神を持つことです。その資質を育てるために本校では「人格の独立」をうたっており、「誠」「個性」「有為の人材」の三つを育てることを教育目標としています。ただ、「誠の精神」といっても、中学生にはわかりにくいので、「誠」とは「うそをつかないこと」と説明しています。たとえば、電車内で座ってスマートフォンばかり見て、目の前の高齢者に席を譲らない生徒がいたとします。「これは誠の精神に反することだよね」と説明すると、生徒にもわかります。
「誠」は坪内逍遙先生によって校訓に掲げられました。坪内先生は学校の創立当初、倫理の授業を担当されていて、「人間とはどうあるべきか」という講義をされたそうです。そういうところから始まった学校なのだと思うと、わたしたちも、伝えるべきことが生徒にきちんと伝わるように話さなくてはならないと思います。
髙宮 わたしはアメリカの大学で大学経営学について学びました。そこでたたき込まれたのは、「ミッション・センタード」と「マーケット・スマート」の二つです。意訳すれば、「何かあれば建学の精神に立ち戻れ」と「時代に合わせて柔軟に対応せよ」ということになります。「不易と流行」ということばもありますが、守るべきものがあって、それを守るために変えるべきところは変えて今の時代のものを取り入れていく、ということだと思います。貴校も早稲田大学も、それを実践されている印象があります。
笹倉 ICT(情報通信技術)が急速に学校現場に浸透していますが、その弊害も起きています。本校は、何事も新しいからといってすぐ飛びつくことはしません。それまでに培ってきたものにも価値がありますから、それを捨てて新しいものに飛びつくとしたら、では今までやってきたことには何の価値もなかったのか、ということになります。新しいものを取り入れるにしても、普遍的な教育を貫いてきた学校なら、その本質は変わるものではありません。

◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎