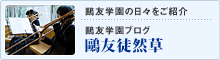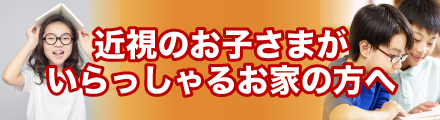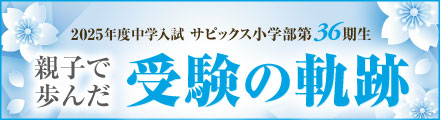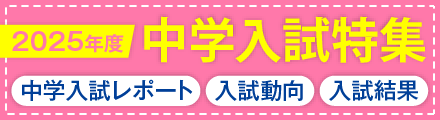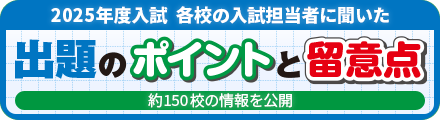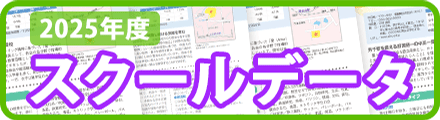さぴあインタビュー/全国版
多様な経験を盛り込んだ
バランスの取れた教育を通して
確かな学力と豊かな人間性を形成
早稲田中学校・高等学校 校長 笹倉 和幸 先生

文系も理系も基本は「全教科を学ぶ」
重視するのは実体験を通した学び

校長 笹倉 和幸 先生
溝端 文系も理系も基本的に全教科を学ぶというお話がありましたが、教育システムについてもう少し詳しくご説明いただけますか。
笹倉 中高時代はいろいろな経験をしなくてはならないというのが、大隈先生の教育理念です。中等教育の段階で経験を積んでいなければ、高等教育から先では伸びません。本校の教育は、多様な経験をきちんと積ませることが大原則になっています。授業でもそうです。学習指導要領にあるすべての教科・科目を経験させなくてはならないという考えから、コース制は敷かず、選択科目のようなものも設けていません。たとえば理科なら、生物と地学は前倒しして、高校の範囲を中学で学びます。高校に入ると、文系でも物理や化学の授業がありますから、そうやって理科の4分野は全生徒が学びます。
溝端 新しい3号館には理科実験室がありますが、地学教室もあるのは珍しいと思います。これもすべての分野をしっかり学ばせるという姿勢の表れですね。
笹倉 3号館には物理・化学・生物・地学の4分野の実験室があり、授業はかなり充実しています。中3では地学実習もあります。埼玉県の秩父盆地で、地質構造や岩石の観察、化石採集などを行うのですが、すごい化石を見つける生徒もいます。特に、物理と化学は実験が非常に多く、理科では昔からそうした体験型学習の時間を多く設けています。

上/新たな3号館には、物理・化学・生物・地学の各分野の実験室が配置され、設備も充実しています
下/興風館1階の図書館。約6万冊を所蔵し、100人が利用できる閲覧スペースもあります
溝端 最近はデジタルツールが充実しているので、理科実験の動画を見せるだけの場合もあります。実際に自分の手を動かし、実験する時間が多いのは、うらやましい環境だと思います。
笹倉 実験を行うには、器具の扱い方をきちんと理解していなければなりません。最近は、理工系の学部でも基本的な実験器具の扱い方がわかっていない学生がたくさんいるそうですね。卒業生から聞いて驚きました。本校では中1からその指導をしっかり行います。
溝端 そうしたていねいな指導もさることながら、主要教科の補習や課外の講習も充実しているそうですね。とてもていねいに教えてくださると、サピックスの卒業生も話していました。
笹倉 特に、中学時代に英語や数学が遅れてしまうと、困ったことになります。英語と数学では、定期試験が終わった後などに補習を実施しています。「人格の独立」をめざすには、どんなことでも自分で正しい判断ができるようにならなければなりません。「この分野はわかるけど、あの分野は知りません」では正しい判断はできません。補習は手間がかかって大変ですが、教員は自主的にやってくれているので、「すべての分野を全員にきちんと学ばせる」という方針は教員のなかに浸透していると思います。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎