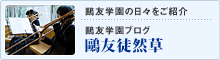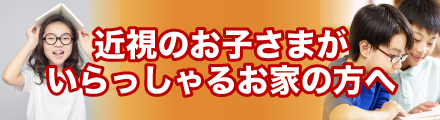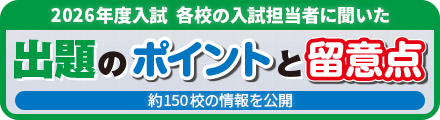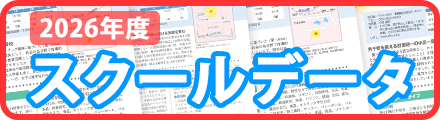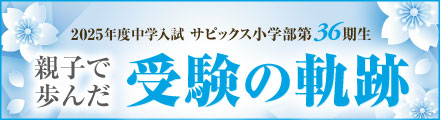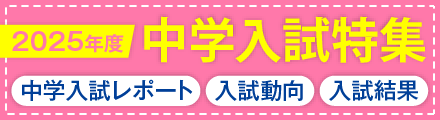さぴあインタビュー/全国版
ゆとりある教育環境の下、
本質的な学びの経験を通して
社会で輝く自分へと成長する
早稲田大学高等学院中学部 学院長 本木 弘悌 先生

「自分で主体的に考えてほしい」
中学開設時に託した教員の思い

SAPIX YOZEMI GROUP
共同代表
髙宮 敏郎
髙宮 早大学院とのご縁は教員として勤務されてからですか。
本木 高等学院とのご縁は2006年に本校の地歴科教諭として勤務してからですね。わたしは、大学院の修士課程を修了後、非常勤講師も含めると3校の大学附属校で教えました。その後、退職して大学院に戻り、博士の学位を取得後、本校の教員として着任しました。偶然にも大学附属校にはなじみがありました。
髙宮 早大学院に中学部ができたのは2010年です。着任されて間もなく設立準備が始まったのではありませんか。
本木 中学部の開設日が決まってからは、急に慌ただしくなりましたね。わたしは開設準備室の副室長を務めましたが、それまでさまざまな附属校に勤めてきた経験が大いに役立ちました。
髙宮 一般的には、旧制中学だったところが戦後に高校になり、新たに中学を設立して一貫校になるという流れが多いと思いますが、早大学院は大学予科が前身ですから、事情は違いますね。中学部を立ち上げる際、どんなことに苦労されましたか。
本木 早大学院は1920(大正9)年、早稲田大学の前身である東京専門学校の予科として設置されました。戦後の学制改革で新制高校になり、早稲田大学のある新宿区戸山町で新たなスタートを切りました。この練馬区上石神井に移転したのは1956(昭和31)年のことで、それから50年以上たってからの中学部の設置です。高等学院はすでに完成した学校で、自由な校風で知られていたので、それをどう中学と接続させるのか、対外的にも内部的にも、理解してもらうのに最も時間がかかりました。「中学もオールフリーの学校になるのだろうか」というイメージを持つ方が多かったのです。もちろん、そんなことはありません。
髙宮 中学生と高校生は同じキャンパスで生活していますが、指導方法は発達段階に合わせて変えるということですね。
本木 制服一つとってもそうです。本校にも制服(詰め襟)はありますが、高校生は私服でもかまいません。しかし、中学生はきちんと着こなしができなくてはなりませんから、着用してもらいます。ただ、中学は厳しくするとはいえ、どこまでにするかが問題です。高等学院や大学に進んでからも活躍してほしいと考えたとき、いわゆる「普通の中学生」にはなってほしくないという思いがありました。
髙宮 型にはめたくない、主体的に判断できるようにしたいということですね。学院長のごあいさつのなかに、「学院には自分を育てるのが上手な生徒が多い」とありました。これはどんな思いで書かれたのですか。
本木 よく「自由な学校」といいますが、それは「選択肢がある」という意味です。入学式でも話しましたが、「選択肢がない状況の国や地域や時代があるなかで、君たちは選択肢がある時代に生きることができる、だとしたら選択しないというのはないよね」と。でも、何をするかは自分で考えなくてはならず、それに対して自分で責任を持たなくてはなりません。ここは「大人の学校」だからです。それができるようになれば、自分で自分を育てられるようになり、将来どこに行ってもやっていけます。そんな話をしました。
髙宮 「自由」とは何をやってもいいということではない、たくさんある選択肢から自分で選ばなくてはならない、だから自分で考える力を育んでいきたいということですね。
本木 そうです。仮に選択肢がなかったとしても、自分でつくればいいのです。
 約1500席の講堂。卒業式などの学校行事のほか、生徒の課外活動や成果発表でも利用されます
約1500席の講堂。卒業式などの学校行事のほか、生徒の課外活動や成果発表でも利用されます
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎