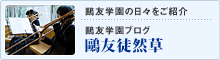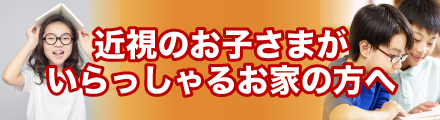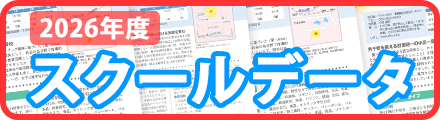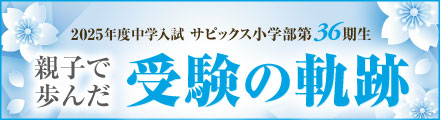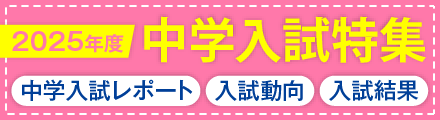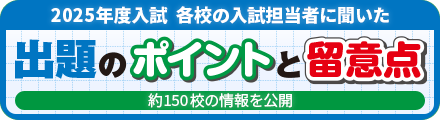さぴあインタビュー/全国版
ゆとりある教育環境の下、
本質的な学びの経験を通して
社会で輝く自分へと成長する
早稲田大学高等学院中学部 学院長 本木 弘悌 先生

受験科目にとらわれることなく
好きなテーマでフィールドワーク

学院長 本木 弘悌 先生
広野 先生は地理がご専門ですが、授業は今も受け持っていらっしゃるのですか。
本木 中学部ができる前は高校で教え、中学部ができてからはその授業を持つようになりました。学院長になってからコマ数は減りましたが、今も高校で教えています。
広野 中学ではどのような授業をされていたのでしょうか。
本木 中学受験を経て入学した生徒たちは、基礎的な地理の知識をほぼ習得していますから、リアルな地理を感じられる授業を心がけました。たとえば、工業の授業では、伝統工芸の生産現場の話をしたり、衣料品づくりやデザインの話をしたり。そのほうが生徒たちは興味を持ちます。もちろん、それはベースとしての知識があってできることです。中学受験は簡単ではなく、入学してくる生徒はすでに一定の知識を持っています。中1生のなかには、地理の授業にサピックスで使っていた地図帳を持ってくる生徒もいました。そういう素地があって入学してくるので、あとはそれをどう伸ばすかという選択になります。
地理の場合は、やはり現地に行くのがベストですね。現地に行く機会があれば、事前にデータや地図を準備するなど指示します。そして実際に行ってみると、事前に調べたとおりではないことがあると気づくのが大事です。高3になると、卒業論文に取り組みますが、フィールドワークをする生徒が集まるゼミでは、夏に出掛けるまでの間に準備をします。
広野 下調べして現地に行き、調査をして最終的に論文にまとめるという、大学のゼミのようなことを高校生が行うわけですね。
本木 本校には研究に対して同窓会から奨励金が出る制度がありますから、旅費のサポートが受けられます。それを使って小さな村に行き、2週間ほど滞在して調査をして帰ってくる生徒もいます。
髙宮 行動力がありますね。地理は大学入学共通テストでも点数が取りづらい科目ですから、あまり選ばれません。地理好きの生徒は一定数いると思いますが、大学受験がないからこそ、そのように興味を持って活動できるのですね。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎